教員インタビュー
吉田 和浩 教授

大学院人間社会科学研究科
国際教育開発プログラム
吉田 和浩 教授
専門分野:教育協力
教育政策と実践の現場をつなぎ、
世界が抱える教育課題に立ち向かう
政策と実践を「つなぐ」ための研究
私の研究テーマは教育分野における国際協力です。現在は3つの側面から国際教育協力に携わっています。1つ目は一研究者として個別の事例研究を論文にすること、2つ目は各国の教育政策実行に携わること、3つ目は政府の関係者と対話して政策決定やその実践に関わっていくことです。それぞれ規模は異なりますが、いずれも政策と実践を「つなぐ」ための課題分析が重要です。

例えば、個別の研究では開発途上国を訪れ、政策が教育現場でどのように展開され、どのような成果に結びついているか、結びついていないとしたらどのような課題があるかを、関係者のヒアリングやデータから分析します。分析後は、政策の浸透状況の評価や現地の教員らとのディスカッションを実施。研究論文として発表するだけでなく、現場の実践へ還元するよう心掛けています。
政策と実践の連携を分析する上では、政策そのものの出来の良さを評価することもあります。2014年から関わったSDGsのアジェンダ策定では、目標4「質の高い教育をみんなに」の項目内容について各国関係者と議論しました。政策評価において重要となるのが「一貫性があるかどうか」という点。政策の目的が現場の実態に合っていなかったり、目的達成に適した課題設定になっていなかったりすれば、実行しても良い結果につながりません。学校に行けない子どもたちのために開発途上国に学校を作っても、その国の社会環境や教員養成などの問題を解消しないと、根本的な解決につながらないのと同じです。SDGsは世界共通の目標なので、各国の実情とアジェンダを整合させるのに苦労しました。
開発に欠かせない社会情動教育
私が研究者になったきっかけは、大学卒業後に就職した商社での経験にさかのぼります。開発途上国で発電所建設の現場監督を担当した際、現地の人々と生活を共にするなかで「開発とは何だろうか」「人が豊かに暮らすとはどういうことなのか」と考えるようになりました。

その答えを見つけるために、海外コンサルティング企業協会の研究員や留学を経て、世界銀行へ入行。ガーナ、ナイジェリア、ザンビアなどの教育プロジェクトを担当し、政府や援助機関と共に、教育政策の策定から実施まで幅広く携わりました。そこでの課題分析や政策評価の経験が、現在の研究へとつながっています。
長年、国際協力に関わるさまざまな仕事をしてたどり着いた答えは、「開発とは人であり、人の開発は、目に見える経済活動や社会活動を通じた外側への開花と、内面の健全な発達とを持ち合わせたものでなければならない」ということ。外側の開発、内面の発達の両輪があるからこそ、より良い社会を構築できると実感しています。
日本では「知・徳・体」の重要性が学習指導要領に明記され、3つのバランスがとれた教育が機能しています。この「徳」にあたる内面の部分に着目した社会情動的スキルとは、心の働きとそれに由来する社会での行動様式を指します。社会情動的スキルが国際的にも注目されるようになったのは、実はここ数年のことです。それまで教育においては、「知」が最重要視されていました。計算や読み書きの能力は、将来仕事に就く上で必要なものだからです。しかし、いくら頭が良くてもそれを悪事に使ってしまえば、社会は悪い方向に転じてしまいますよね。社会性と情動も成長しないと一人一人が豊かになれないし、持続可能な社会は築くことができない。つまり、社会情動的スキルを養う教育は「持続可能な開発のための教育(ESD)」でもあるのです。
山積する課題を解決し、より良い社会を創るために
海外の研究者からは「日本の教育は社会情動教育を備えていて素晴らしい」とよく言われます。ならばそのノウハウを海外へ伝えればいいと思われるかもしれませんが、そう単純なものではありません。国が違えば、住んでいる環境や文化も異なります。また、社会で生きる力を養う教育は、各国の社会状況に大きく左右されます。日本社会の中でうまく機能している理由や特徴を整理して初めて有用なモデルとなり得るのです。
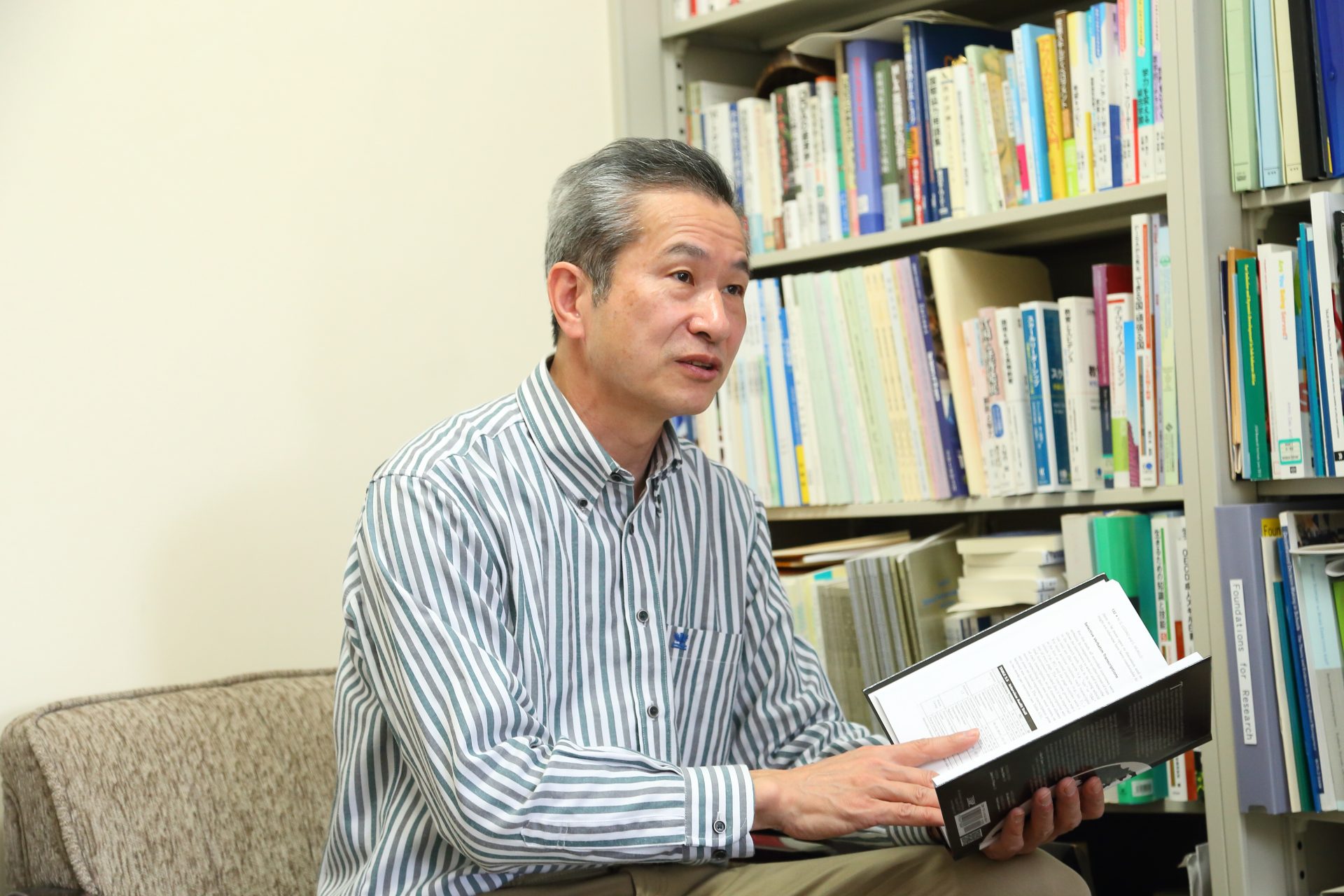
教育には「特効薬」がありません。学校現場によって教員も生徒も違う。教育内容も時代によって変わっていく。条件が一つ一つ違うなかで、山積する課題を解決するには息の長い研究が必要です。そのために私が心掛けているのは、世代や国を超えて多様な人と意見を交換し、交流すること。研究者一人一人のリソースは限られているため、ナレッジやノウハウの共有が少しでも早い解決に至ります。私が重視する「政策と実践をつなぐ目」をできるだけ多くの人に伝えることで、現場に整合した政策が広まり、より良い社会に貢献できると信じています。
平和を希求する大学で学ぶ国際教育開発
ユネスコ憲章の前文に「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」という記述があります。第二次世界大戦が終わったころから、平和と教育は不可分だったのです。そこに鑑みても、平和を希求する精神を理念に持ち、長年教員養成や教育研究で貢献してきた広島大学は、教育開発研究における大きな使命を負っていると考えています。

日本の教育研究機関は、知見を必要とする学校やJICAなどの国際協力機関との連携がまだまだ不十分です。国際教育開発の研究者はそれらを研究によってつなぐ非常に重要な役割を担っているのです。
本プログラムは前身の国際協力研究科のころから、教育現場での実践を見据えた研究を非常に重視しています。実践に問題意識を持った教員や業務経験豊富な留学生が所属。多岐にわたる分野の専門性を備えており、国際教育開発を学ぶには最適な環境です。教育学部出身者に限らず、自国の教育への問題意識をしっかりと持った人や、将来的に教育分野での実践に携わりたい人の入学をお待ちしています。
齊藤 一彦 教授

大学院人間社会科学研究科
国際教育開発プログラム
齊藤 一彦 教授
専門分野:スポーツ国際開発学
体育やスポーツの価値を国内外に発信し、
社会課題を解決する
青年海外協力隊で気付いた、体育科教育の重要性
皆さんは「スポーツと国際協力」と聞くとどのようなものを思い浮かべるでしょうか。おそらくピンとこない人も多いと思います。私もそんな若者の1人でしたが、大学卒業後に青年海外協力隊に参加したことで意識が変わりました。陸上競技の経験を生かしてスポーツ指導をするため、中東のシリアに行ったのですが、現地には日本のような体系的な体育が行われていない学校が多くありました。

日本にいる間は体育があるのが当たり前で、その意義や役割なとについてほとんど意識をしていませんでした。しかし、シリアの子どもたちの運動能力や、転び方などを見ているうちに、「体育で習う鉄棒やマット運動等の運動が、体の操作感覚の習得に役立っているのでは」とあらためて強く感じるようになったのです。また、協力隊の活動を経て、スポーツが盛んな地域はそうでない地域に比べて人々が明るく、倫理観が備わっている傾向があることにも気付きました。スポーツが社会の発展に寄与するのではないか、体育やスポーツの持つ役割についてもっと追究したいと考え、研究の道に進みました。
大学院に入り研究の初期段階で、日本とシリアの子どもたちの体力測定結果を比較してみました。すると、筋力、筋持久力などの基礎体力は同程度だったのですが、瞬発力や敏しょう性などでは、日本がシリアを大きく上回りました。体力テストで言うと、反復横跳びや立ち幅跳びなどが該当項目ですね。日本人の方がそれらのスコアが高かったのは、体育の授業が体系的に行われているからだと思います。瞬発力や敏しょう性などの能力は、子どもの頃に身に付けないとその後に発達しにくいもので、体育がそれらを伸ばす役割を果たしていることに改めて気づかされました。
これらの経験から、体育・スポーツの国際協力の意義や重要性を実感し、現在は体育・スポーツが社会開発にもたらす役割などを検証する研究を行っています。
開発途上国の体育科教育を取り巻くさまざまな課題
開発途上国では、スポーツに取り組みたくても取り組めない環境が多くあります。例えば、学校には部活動のようなものがなかったり、体育の時間があっても授業としてきちんと実施されていなかったり。交通が発達しておらず、競技場などのスポーツ施設に行きたくとも、気軽にアクセスできないという事情もあります。

また、それ以前に体育が軽視されがちであることも要因です。私は海外の教育関係者から体育の存在意義について問われることがあります。その際、以下の3つの理由を伝えたりしています。1つ目は、体格、体力・運動能力の発育・発達に大きな影響を及ぼすこと。特に人間の発達メカニズムでは、年齢によって身に付く能力が異なります。子どもの頃にいろいろな運動を行い、特に自分自身の体をコントロールできる運動能力を身に付けておかないと、日常生活で大けがにつながるリスクがあります。また、幼い時期からスポーツに親しんでおくことで、運動する習慣が身に付き、将来的に肥満や疾病を防ぐことにもつながります。2つ目は、人格形成において体育・スポーツが果たす役割は大きいということ。順番を守る、ルールを守りながら、仲間と力を合わせるという経験は、社会の発展においても重要です。3つ目は、適度な運動が脳の発達に良い効果をもたらすこと。開発途上国においても、大学等へ進学し、学歴を有することがその後の収入に大きく影響します。また、「運動する暇があったら勉強するべき」という風潮も多くあります。しかし、脳科学では運動が記憶力などの能力向上に貢献すると証明されており、正しく運動を行うことは学力を高めることにもつながるのです。
スポーツがもたらす、社会的な価値
スポーツ国際開発学の研究は海外を対象にすることが多く、国内で完結する研究と比べて日本の教育の良さや課題がよく分かります。日本の強みは、スポーツが教育の延長線上にあること。学校の授業の中で教わるので、「正しく」スポーツを行えます。勝ち負けを競うスポーツは、場合によっては争いや暴力のきっかけとなり、社会を悪い方向に導く危険性もありますが、それを正しく良い仕組みとして構築できる日本の体育科教育は素晴らしいと思います。

一方で、部活動などで、不必要に厳しい指導が行われ。スポーツが本来持つ楽しさや自由が失われているという課題も感じています。私の研究の一番の目標は開発途上国の教育を改善することですが、比較検討によって得た客観的な評価の視点を活用し、日本の体育科教育をより良くすることにも貢献したいと考えています。
また、スポーツの価値を提示することも目標の一つ。スポーツには「遊ぶ」「楽しむ」「発散する」などの要素もありますから、社会課題や経済的困難を抱える国ではどうしても優先順位が低くなります。また、数学などの科目とは違い、体育科教育は効果が目に見えづらく、即効性もありません。それでも、体育やスポーツが浸透することで社会に与える影響は確かにあります。例えば、スポーツには健康維持や競技力向上という側面以外にも、集客力を活用して地域経済の発展に寄与したり、競技への参加を通じて民族同士のわだかまりを解いたりと、社会課題を解決する力があります。それを客観的に捉えるのがスポーツ国際開発学の研究です。
スポーツ国際開発学は、可能性を秘めた未発達の分野
私が専門とするスポーツ国際開発学は、先行研究がまだまだ少ない未発達領域なので、いろいろなことに挑戦して、新しい分野を開拓していかなくてはなりません。ぜひ挑戦意欲のある学生に入学してほしいと思います。英語に自信がなくても、入学後に学べばいい。若い皆さんは環境さえ整えばあっという間に成長します。本プログラムには留学生がたくさん所属していますので、国内にいながらさまざまな国の人と学ぶことができますよ。

国際教育開発には、言語教育や地域カリキュラム開発、教育政策などさまざまなアプローチがあります。その中でも体育やスポーツは言語の壁を乗り越えやすく、全世界共通のルールがあるため、取り組むハードルの低い分野です。何より、やっていて楽しい。国や文化が違っていても共通理解を生みやすいので、国際協力の導入に適していると思います。他の分野と連携すれば相乗効果も期待できるでしょう。皆さんも一緒に体育やスポーツの持つ価値を考えてみませんか。
川合 紀宗 教授

大学院人間社会科学研究科
国際教育開発プログラム
川合 紀宗 教授
専門分野:特別支援教育、
インクルーシブ教育
「学びにくさ」「生きにくさ」を感じている
全ての子どもたちへ充実した教育支援を
生きにくさを感じる人々の支えとなる
私の主な研究テーマは言語障がいのある人への特別支援教育です。社会生活を営む上で重要となる言語運用やコミュニケーションが困難であると、本人は「生きにくさ」を感じてしまいます。障がいがからかいの対象となったり、生きにくい状況が自己肯定感を低下させたりすることで、自殺にまで至ってしまう場合もあります。

そこで、本人やその家族が障がいをどのように受け入れているのか、私に何か支援できることはないかと考え、研究を始めました。中でも吃音を研究対象としているのは、障がいのある人の心の内を知るためです。吃音の方々は話すことが苦手なだけで、障がいのない人と同じように思考しているので、障がいや生きにくさの捉え方について聞き取り、障がいのある人に対するより良い支援につなげられるよう研究を進めています。
私の研究室では、主にインクルージョンや特別支援教育に関心のある学生が世界中から集まります。彼らのほとんどは留学生で、修了後は多くが本国の特別支援教育や教員養成に携わります。指導の中で伝えているのは、子どもに寄り添ってほしいということ。発話やコミュニケーションに障がいのある子どもは、自分の気持ちをうまく言葉に置き換えられず、暴力で示してしまうこともあります。そうした表面的な行動で判断せず、子どもが本当に訴えたい内容をしっかりと理解することが効果的な支援につながります。また、子どもからの発話がないとつい大人の方から話しかけてしまいがちですが、それではいつまでも子どものコミュニケーション力は育ちません。言語での表現がなくとも、表情や視線など細かな子どもの動きを捉え、別の形でのコミュニケーションをじっくりと待つ努力も必要なのです。
制度や技術で教育支援を変えていく
私は本学教育学部で特別支援学校の教員養成にも携わっていますが、特別支援教育やインクルーシブ教育を推進するには、さまざまな角度から適切な教育的支援の在り方を検討する必要があります。外部の専門家との協力も一つの方策です。

例えば教員が特別支援学級に在籍している児童に対して個別の指導計画や教育支援計画を立てる際、保護者や本人にヒアリングすることはもちろんですが、過去に通っていた療育センターや幼稚園などの教職員、言語聴覚士や特別支援教育コーディネーターなどの専門家、近隣の特別支援学校、私のような研究者などからの協力を得ることが望ましいと考えます。複数人の専門家がチームを組み、多層的な指導・助言を行うことで、本人にとってより適切な支援を行うことができます。このような仕組みは既に作られているのですが、ボランティア精神に頼る部分が大きいのが現状です。全ての子どもたちに十分な支援を行き渡らせるため、連携に専従できる人材や部署を設けるなど抜本的な改善が必要だと感じています。
また、教育制度の改革も欠かせません。通常の学級にも、障がいとは診断されていないものの、学びにくさや生活のしにくさを抱えた児童生徒が小中学校に約6.5%います。そのような児童生徒にも支援を行うべく、現行の学習指導要領では、全ての学校において特別支援教育を推進することの必要性が明記され、そして学習指導要領の解説では、各教科において学びにくさのある児童生徒に対する具体的な支援方法が例示されています。これにより、教員は特別支援教育に関する知識が十分でなくとも、学びにくさを抱える児童生徒に対してどのような工夫を行えばよいかをご理解いただけようになりました。中央教育審議会の専門委員として、文部科学省に対して直接提言できる機会がいただけたのはありがたいことです。今後も特別支援教育のカリキュラムや指導法の改善に関する研究成果を還元し、全ての子どもたちにとって学びやすい教育を実現していきたいです。
今後はデジタル技術を用い、特別支援教育のDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めたいと考えています。例えば、VR(仮想現実)を用いた発声発話練習。吃音のある人の中には、1人だとすらすらしゃべれるのに、人前など特定の場面でのみ症状が現れるという人も多く存在します。そこで、VRで苦手な場面を再現できれば、1人でも練習が可能です。コロナ禍を通して、本人のみで発声発話練習ができる環境作りも必要だと感じました。このようなバーチャルな環境で学べる技術が発達すれば、教育実習などにも応用できるでしょう。また、インクルーシブなデジタル教科書の開発も期待されています。デジタル教科書には、音声や動画を活用することで、より分かりやすい授業が実現できるなどのメリットがあります。教科書の開発には、特別支援教育だけでなく、教科教育や心理学、情報工学の研究者にも携わっていただきたいと考えています。
誰ひとり取り残さない教育を実現する
国際教育開発プログラムでは、インクルーシブ教育に重点を置いて研究を行っています。これは、人種や性別、障がいの有無などに関わらず誰ひとり取り残さない教育のことで、もともとは特別支援教育において、障がいのある児童生徒と無い児童生徒が同じ教室で学ぶことを指していました。

そこから派生し、マイノリティに当たる人々がマジョリティに当たる人々と共に学び、教育や社会に包含されることを目的としています。しかし、一概に全ての児童生徒が同じ教室で学べば良いというわけではありません。国の文化や宗教などによって、教育への考え方や常識はさまざまです。例えばサウジアラビアでは、インクルージョンを推進するために、障がいの有無を問わず児童生徒が同じ教室で学んでいる学校はありますが、男女を同じ教室で学ばせることには抵抗感が強かったりします。画一的な概念を定めてしまうと、逆に各国の多様性を受け入れられなくなってしまうため、柔軟性をもってより良い教育の在り方を考えていかねばなりません。
真のインクルーシブ教育を実現するためには、特別支援教育を前面に押し出した現状からいかに脱皮するかが大切だと考えます。インクルーシブ教育のベースにあるのは、学びにくさを感じる全ての生徒に対して支援を行うイギリスの教育文化です。生徒のニーズに対して教育支援を行う考え方はまだ新しいため、あまり研究が進んでいません。病理的な専門知識が必要な従来の障がいに関する研究と比べ、本来間口の広い分野であるはずですが、研究が特定のテーマや手法に偏っている現状があります。私自身は、インクルーシブという考え方を教育制度に取り入れる研究や、子どもや保護者のマイノリティに対する意識の調査、教員研修などを行っています。障がいや特別支援を専門とする研究者だけでなく、ジェンダーなどさまざまな分野の研究者が参画し、学際的に発展させていければと考えています。
研究に加え、今後インクルーシブ教育の本格導入を考えている国に対して、制度設計の助言なども行っています。例えばインドネシアでは、障がいのある児童生徒が通常の学級に在籍していれば、その学級のことを「インクルーシブ学級」と呼んでいますが、実際に適切な配慮や支援が行えているかまでは突き詰めて考えられていません。そこでインドネシアの教育文化省から依頼を受け、日本の文部科学省と組んで制度設計を行ったり、教員養成系の大学と共同研究に着手したりしています。
あらゆる多様性が認められ、「違い」に価値が見いだせるようになることがインクルーシブ教育の理想です。少子高齢化によって就労可能人口が減少する日本では、将来さらに海外から人材を受け入れる必要に迫られるでしょう。その時には、自分たちと異なる文化や言葉、肌の色などを受容し、マイノリティに当たる人々と共に日本社会を築いていかねばなりません。そのためにも、将来の日本を担う子どもたちには、インクルーシブな環境の中で学び、マイノリティに対する正しい認識や態度を身に付けてもらいたいと考えます。
多様な学びを社会の発展に役立ててほしい
国際教育開発プログラムの特徴は、他プログラムと比べて多様な教員が在籍しているところだと思います。グローバルな課題に対して一つの分野に収まらず、さまざまな視点から指導を受けることで、視野が広がるのではないでしょうか。

本学大学院には主指導と副指導の教員による共同指導制度があり、博士課程の学生は主指導教員1人と専門の異なる教員を含む2人以上の副指導教員から指導が受けられるため、他プログラムとの連携も可能です。教員自身もさまざまな学生を担当することで、新たな学びにつながる部分もあります。多様な専門分野がありつつも、それらが分断されずにつながっているところが本学のユニークなところだと思います。
教育は未来を創る仕事です。博士課程を修了すると博士号がもらえますが、学位や名誉を得ることが重要なのではありません。自身が学んだ知識や専門性を次の世代のために生かし、社会に役立てたいという志ある人は、ぜひ本プログラムで共に研究に取り組みましょう。
佐藤 暢治 教授

大学院人間社会科学研究科
国際教育開発プログラム
佐藤 暢治 教授
専門分野:言語学
中国奥地で現地の青年と辞書を作り上げ
消滅の危機が迫る言語を記録する
言語は文化の多様性を示す指標であり、人間の可能性
私は言語学が専門で、特にモンゴル系の危機言語を研究の対象としています。言語というものは話者がいなくなることで消滅していくものですが、それは遠い国の少数民族の言語で起こっているとは限りません。私たちになじみ深い方言にも、言葉の消滅は見受けられます。例えば、広島方言には、標準語の「雨が降っている」に相当する二つの表現があります。

「雨が降りよる」は今まさに雨が降っているという意味で、進行を表します。「雨が降っとる」は、現在雨は降っていないが、路面が濡れているような場合に用い、結果を表します。わずかな語尾の違いで微妙なニュアンスを伝える広島方言ですが、広島に住んでいる人にこの二つの違いをたずねても正確に答えられない人が増えています。標準語にない地域特有の表現は、現代の広島では消えつつあるのです。
世界では多くの言語が消滅の危機を迎えており、言語学者の中には21世紀には現存する6000~8000の言語が半減すると言っている人もいます。英語や中国語など社会的影響力の強い言語を運用できるとビジネスなどで有利になるため習得が進みますが、反対に、使用人口が少ない言語は仕事上生かせる可能性が小さいため、受け継がれなくなるのです。
言語が消えるというのは文化が一つ消えるということであり、ひいては文化の多様性が失われることにつながります。人間の可能性を狭めるこの危機を回避するため、言語学者は言語の社会的・文化的状況を調査し、記録しています。
謎が多い保安語を研究するために中国奥地へ
モンゴル系の言語である保安語は、中国の西北部・甘粛省臨夏回族自治州に住む総人口約2万人の少数民族・保安族が母語としていますが、中国語を日常的に話すようになったことで民族の言葉を使用する若者が減少しています。

モンゴル語専攻だった学生時代に「中国の奥地で変わったモンゴル系の言語が話されている」と聞いていた私は、周辺地域でも特に研究が進んでいなかったこの言語に興味を持ちました。保安族が暮らすのは、日本を出発してから現地に到着するまでかつては丸3日もかかった中国の山岳地帯です。言語学者が足を踏み入れないどころか、外国人の立ち入りさえままならない状況でしたが、現地に向かい、好奇心の赴くままに研究を始めました。
実際に現地の人が話す保安語を聞いてみると、モンゴル語とはおおきく異なります。どのような歴史をたどったのか判然としない保安語の全体像を把握するために、まずは語彙を書きとめ、文法体系を把握する作業に移りました。
現地の青年と10年の歳月をかけて辞書を完成
保安語の研究を進めていた2004年ごろ、保安族の有力者から手紙を受け取ります。そこには、保安語の辞書を作ろうとしている一人の若者に協力してほしいとつづられていました。言語学者は基本的に言語の記録に重きを置くため、辞書や文法書の作成を自発的に始めることはありませんが、社会貢献のため現地社会の要請に協力することは多々あります。

今すぐ研究に役立つわけではなくても、20年後、30年後の未来において、現地社会と研究者の双方に重宝されると考えて、喜んで協力したいと快諾しました。
以来、私と青年・馬沛霆(Ma Peiting)の10年にわたる辞書作りがスタートしました。「目」や「食べる」など日常で使用される頻度の高い基礎語彙から始め、次に民話や普段の日常会話に登場する単語・複合語まで範囲を広げ、母語話者に発音してもらっては発音を書きとっていきました。作業を進める中でとりわけ頭を悩ませたのが発音と文字の対応です。一般の人にも理解してもらうには、国際音声記号ではなく中国のピンイン式ローマ字を用いて辞書を作成する必要があります。保安語は固有の文字を持たないので、どの発音にどのローマ字をあてはめるか、保安語の話者がローマ字から単語を読み取り発音できるか、確認しながら地道に作業を進めました。特に母音については骨が折れました。保安語には母音が6つあるため、母音が5つしかないローマ字と簡単には対応させられないのです。ほかにも老人と若者で発音が異なることに気づいて一から調査をやり直したり、地域ごとに訛りがあるのでどの地域の発音を記載するかを吟味したりと、苦労が絶えませんでしたが、幾度となく壁を乗り越え完成に至りました。
現在、馬沛霆の希望により保安族の民話集の作成を始めています。社会貢献だけでなく言語研究の側面からもアプローチを続け、まだまだ謎が多い保安語の言語現象に関して解明を進めます。
フィールドに出かけるからこそ発見がある
言語研究を続けてきた私が大切にしているのは、文献研究に終始せず、フィールドに出かけることです。語彙を収集する際、調査中ではない食事の席でふと面白い表現が出てくることがありました。今では多種多様なオンラインシステムが登場し、聞き取り調査はそれで事足りるかもしれません。

しかし、現地に行って研究対象とする言語のネイティブスピーカーたちと膝を交えて話すことで、意外な発見に巡り合えます。本プログラムを志す学生には専門分野に関する知識や、国際社会に対応できる柔軟性だけでなく、フィールドに出かける気概を持ってほしいと考えます。
現在、研究室には日本語をはじめとするさまざまな言語に興味を持つ学生が集まっています。フィールドで実施する言語調査に参加してみたい、そんな思いを抱いている方はぜひ一緒に学びを深めましょう。
中矢 礼美 准教授

大学院人間社会科学研究科
国際教育開発プログラム
中矢 礼美 准教授
専門分野:地域カリキュラム、
平和教育、
グローバルシティズンシップ
平和な世界を創る教育を目指す
お互いを鏡として多様性を認め合う比較教育学研究
私がインドネシアの研究を始めたのは、大学時代の出来事がきっかけでした。インドネシア人の友人から、第二次世界大戦中に日本がインドネシアを植民地支配していたと聞かされ、友人の国に対する自国の行いについて無知だったことに強くショックを受けました。

改めて世界史の教科書を読み返しても「日本軍が南下した」としか記載されていませんし、図書館中を探しても詳しく記載されている本は見つかりません。これではいけないと感じた私は、日本がインドネシアに与えた影響や現在の状況を広く伝える必要があると使命感を抱きました。当時は教育学部に所属していたため、大学2年生からインドネシアの教育に関する卒業論文に取り掛かり、3年生では学校のフィールドワークも実施しました。国家の近代化と教育の機能、先進国と途上国の間の世界システム論に注目しながら、インドネシアの人々が、国家の独立を経て、国家の統合と開発に向けて、どのような国民形成教育を実施してきたのかについて研究を始めました。よくよく調べると既にインドネシアの社会や教育研究の大家はいらっしゃったのですが、自分らしい見方で研究を進めていくことを目指しました。
大学教員になった今もインドネシアをフィールドに研究を続け、日本をはじめとする世界中の教育制度や文化と比較検討しています。インドネシアには、教育に新しい考え方や技術を積極的に取り入れる姿勢があります。コンピテンシーカリキュラムもその一つ。コンピテンシー(=生きる力)という言葉の通り、社会で生き抜くための能力の習得を目標とし、逆算して学校で何を学ぶべきかを決定します。例えば、民主主義を守るため、デモを成功させる能力を身に付けるべく、計画から行進の仕方までを授業で扱う学校もあります。インドネシアでは軍事独裁政権の末期から教育の地方分権化が進められ、地域の人々による教育開発が行われてきました。様々な教育改革で国を変えていこうという強い意志と行動力は、日本にはない素晴らしい点だと感じています。ただしそこには教育改革を十分に行う制度設計や充実が図られる以前に一部の改革を行うために整合性を失うことも多々あります。そのような点を指摘する際には日本や他国の制度からの視点を用いることとなります。
例えば、日本の教育制度の中でインドネシアの行政官や教員たちに紹介して高く評価されてきたのは、学区制です。学区内の子どもたちを同じ学校に通わせ、保護者と地域と学校が三位一体となって育てることで、学校への愛着を形成できるからです。学区制のないインドネシアでは、裕福な家庭の子どもは送迎により遠方のレベルの高い学校に通えるため、貧富の差が教育格差につながっているという実情や地域カリキュラムを学校がコミュニティとともに実施しづらいという問題がありました。また、もう一つ日本特有の美点として挙げられるのは他人に迷惑をかけないための規律を徹底的に教育する文化です。細かいルールを小さい頃から教え込まれることにより、私たちは無意識のうちに周りに迷惑をかけないよう振舞っています。これらは日本が世界に誇る立派な制度や文化ですが、そのまま他国で導入すれば良いかといえば、そうではありません。学区制の前提には、日本のように先生が学校間を流動的に異動し、教育の質が担保されていることがあります。インドネシアでは現在は学区制を取り入れようとしていますが、日本のような教員配置制度が未整備であるため、実際には多くの問題が指摘されてうまくいっていません。また、規律を守ることは大切ですが、周囲に迷惑をかけまいと気遣うあまり、自分の意見を言えなくなるという負の面もあります。インドネシアの学校では、自由な発言は教室内で多くみられます。また先生がベビーシッターを雇えない日には、授業を受けながら生徒が先生の子供の見ていることもあります。お互いに迷惑をかけて助け合える文化も素敵ではないでしょうか。
教育制度や文化を比較することで、お互いを鏡として双方の教育の特徴を明確にし、より深く理解できます。優劣を付けずそれぞれの在り方を認め合うことを大切にしたいと思います。
教育の選択肢は幸せにつながる
インドネシアは約1万3000の島々からなる世界最大の島嶼国家であり、約400もの民族から構成されています。政治や社会、文化、経済、宗教、歴史、地理的条件などがさまざまであるため、地域によって教育の位置づけは異なります。したがって、国やユネスコなどの国際機関による一律の教育政策やプログラムだけでなく、地域の多様な文化やニーズに沿ったカリキュラム(地域カリキュラム)が必要です。

日本の義務教育における「総合的な学習の時間」のようなイメージでしょうか。実際にそれぞれの地域において必要な教育は、各地域と教育の関係について良く理解している専門家でないと分かりません。このような背景があり、私は地域そのものや地域カリキュラムについても研究しています。
研究者として意識しているのは、万人にとって“良い”教育は存在しないということです。人それぞれ幸せの形もそれへのアプローチも異なるため、誰もが偏差値の高い学校や人気の就職先を目指す必要はありませんし、中レベルの学校や給料でゆるやかに暮らすのも一つの選択肢です。さまざまな考え方を持つ人々が自分に合った選択肢を柔軟に選び、各々の幸せを実現していける環境づくりに寄与したいと思います。
平和は地域の人々の手で創るもの
私はJICAの平和教育研修コースでコースリーダーを務めていたこともあり、平和教育やグローバルシティズンシップの研究も行っています。グローバルシティズンシップとは、平和教育をグローバルな視点で行う方策について考えるものです。

平和教育で大切なのは、その国の人々が自ら平和を築けるようになること。途上国の人々が自分たちで教育を開発し、実践と評価を繰り返して平和な社会を創るお手伝いができればと考えています。平和教育においては、まずさまざまな形の暴力について理解を促します。暴力とは殴る蹴るといった直接的、物理的なものだけではなく、貧困など社会構造に由来するものも含みます。多様な暴力に敏感になり、自分が暴力を振るったり振るわれたりする現状に気付くことが、暴力をなくす第一歩と言えるでしょう。次に、暴力の根本的な原因について考えます。自国に多くみられる暴力の形態とその原因が分かれば、それを断ち切るために必要な教育が自ずと明らかになります。
途上国の人々が自ら国の在り方について考え、未来を描いていくことに意味があると考えるのは、インドネシアのアンボン島での経験があるからです。現地の人々が自分たちの歴史を知り、それを基に築く未来を切り開くのを支えることが私の役割だと思いました。アンボン島はかつて宗教抗争があった土地で、私が訪れた際、復興のために平和教育カリキュラムの作成を依頼されました。しかし、私は依頼を断りました。なぜなら、何世紀にもわたる現地の人々の確執やその克服の「歴史」あるいは実情を知らない部外者が、カリキュラムを提案すべきではないと考えたからです。私にできるのは、カリキュラムの作り方や他地域での地域カリキュラム開発と実施の失敗例を伝えることだけでした。また、私が島の発展と教育の歴史を調べていたところ、歴史家の先生に「歴史を知りたければ、本を探すのではなく現場に目を向けなさい」と助言されました。アンボンに残っている歴史書は、オランダ領であった当時の様子がオランダ語で記された本をインドネシア語に訳したものに過ぎません。その地域の「歴史」は、今を生きる人々が取捨選択しながら描くものだと教わったのです。これからの島の平和の歴史の創造は、当事者が過去の「歴史」の振り返りと教育を通して実施していくものであり、部外者は必要とされる場合にのみ、役立つ情報やスキルを示していくことが大切です。どこかの国の平和教育を真似するようなことや押し付けるようなことがあってはなりません。
一歩ずつ幸せを実践していく
先進国から途上国への一方的な支援ではなく、お互いに学びあい、助け合う形が国際協力の理想です。よく「途上国の子どもたちを救済したい」という人がいますが、大それた目標は必要ありません。

大学生の頃、私が国際開発系の仕事に就きたいと母に伝えた時、まず家のお風呂を洗うよう言われました。自分や家族のために家事もできない人が、海外の人々の役に立てるはずがないと教えられたのです。身近な人を大切にすることから始めて、他人の幸せに地道に貢献できる人が、国際協力において多くの人を幸せにできるのではないかと思います。
国際教育開発プログラムには、誰とでも平和なつながりを築ける人に入学してもらいたいです。研究の中で出会う世界中の人々と切磋琢磨しながらそれぞれの国の教育の在り方について議論し、助け合い、学びあえるプログラムにしていきたいと思います。
